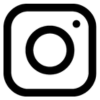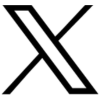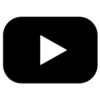知らなかったでは済まない!ノベルティ制作で気をつけたい商標の基本とリスク対策

本記事は、ノベルティ制作会社「コシオカ産業株式会社 MONOCOTO Design Lab事業部」が執筆しております。
「商標って何を気をつければいい?」「トラブルを防ぐには?」と疑問を抱えていませんか?
ノベルティは、企業の魅力を伝え、関係性を深めるための大切な販促ツールです。
しかし、使うロゴやフレーズによっては、商標権の侵害につながるリスクもあります。
知らずに制作してしまうと、思わぬトラブルや信頼低下を招くこともあるでしょう。
本記事では、ノベルティ制作時に注意すべき商標の基本知識やよくあるNG例、トラブルを防ぐ対策についてわかりやすく解説します。
ノベルティを活用したい販促担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
\ノベルティ制作の実績多数!/
ノベルティ制作における商標の基本知識

・商標とは?
・どんなものが商標の対象のなるのか?
・商標の使用には必ず許可が必要になる
商標とは?
ノベルティを制作する際、意外と見落とされがちなのが「商標」の問題です。
商標とは、商品やサービスの顔となる名前やロゴなどを、他人に真似されないよう保護する制度です。
たとえば企業ロゴ、商品名、有名なキャッチコピーなど、魅力的に見えるものや言葉の多くはすでに誰かの権利によって保護されている場合があります。
これらは「商標」として特許庁に登録されており、無断で使用すると商標権の侵害となります。
商標権を持っている人以外が無断で同じ名前やロゴを使うと、商標権の侵害とされ、法的な責任が問われることがあります。
ノベルティ制作では、こうした商標をうっかり使用してしまうことが多く、販促担当者は最低限知っておくべき知識です。
正しい知識を持ち、安全に使える素材だけを使用することで、信頼あるノベルティ制作が実現できます。
どんなものが商標の対象のなるのか?
商標として保護されるのは、ただの「名前」や「ロゴ」だけではありません。
最近では、音や色、立体的な形状、位置なども商標登録の対象になりますが、ノベルティ制作において特に気をつけたいのは以下の3つです。
・商品名
・ロゴマーク
・キャッチコピーやフレーズ
商品名やロゴ、キャッチコピーには商標が登録されている場合があり、無断使用はトラブルのもとになります。
たとえ一般的な言葉に見えても、人気の飲料名やフレーズなどは保護対象であるケースも多いです。
ノベルティに使う前には、必ず権利の有無を確認することが重要となります。
商標の使用には必ず許可が必要になる
登録商標をノベルティに使いたい場合、商標権を持っている人から明確な許可を得る必要があります。
勝手に使ってしまうと、商標権の侵害となり、差し止め請求や損害賠償、さらに悪質と判断された場合は刑事罰の対象になることもあります。
「これは大丈夫だろう」と自己判断せず、使用したいロゴや名称がある場合は、まず商標登録されているかを調べ、その上で必要なら権利者に連絡を取って使用許可を取りましょう。
また、許可が出た場合でも、「使用方法」「範囲」「期間」などまで確認しておくことが大切です。
許可を取ったつもりが、実は条件を逸脱していたというトラブルもあるため、口頭でのやりとりではなく、書面での確認をおすすめします。
ノベルティ制作で起こりやすい主な商標トラブル3つ

・【ケース①】他社のロゴをそのまま使用する
・【ケース②】パロディや類似デザインを使用する
・【ケース③】社内配布や非売品で使用する
【ケース①】他社のロゴをそのまま使用する
ノベルティ制作で最も多いトラブルのひとつが、他社のロゴやブランドマークを無断で使用してしまうケースです。
たとえば、人気の飲料メーカーや家電メーカーなど、知名度の高い企業のロゴを記念品に入れて配布するような行為は、商標権の侵害にあたります。
たとえ「販売目的ではない」「ちょっと使っただけ」だとしても、商標権は“登録された使用者”だけが使えるものです。
無許可での使用が発覚すれば、ノベルティの配布停止や回収、損害賠償を求められる可能性もあります。
ブランドイメージを勝手に利用されることは、権利者にとって深刻な問題です。
軽い気持ちで作ったノベルティが、会社の信頼を揺るがすリスクにつながるので注意しましょう。
【ケース②】パロディや類似デザインを使用する
商標トラブルは、「完全に同じもの」を使った場合だけに限りません。
よくあるのが、有名ブランドやキャラクターの“パロディ”や“オマージュ”を使ってノベルティを作るパターンです。
「よく見れば違うけど、なんとなくあのブランドっぽい」と思わせるようなロゴや配色は、消費者が混同する可能性があるため、商標権の侵害に該当する恐れがあります。
法律上は、類似の範囲でも商標の効力が及ぶため、「似ているだけ」「意識しただけ」といった言い訳は通用しません。
パロディは面白く見える反面、権利者からの警告や法的措置を受けるリスクが高い領域です。
遊び心で作ったつもりが、思わぬ代償を招くこともあるため、慎重な判断が必要となります。
【ケース③】社内配布や非売品で使用する
社内配布や非売品だからといって、商品名やロゴなどを無断で使用するのは問題です。
商標権の侵害は、営利目的かどうかに関わらず成立する場合があります。
たとえば、社内イベントで使用する記念グッズに他社のロゴを使ったり、限定配布のキャンペーングッズに人気キャラを入れたりすることは、たとえ非売品であってもリスクがあります。
また、昨今はSNSやブログなどで社内の様子を紹介する企業も多く、本来社内限定だったノベルティの存在が、意図せず外部に拡散されることもあるでしょう。
外部にもれた場合、ブランドの無断利用として指摘を受ける可能性が高まります。
安心して使えるノベルティを作るには、社内向けであっても“権利の確認”を怠らないことが重要です。
ノベルティ制作で商標トラブルを防ぐ対策3つ

・【対策①】使用素材は権利がクリアなものを選ぶ
・【対策②】制作時にチェックリストを活用する
・【対策③】信頼できる制作会社に依頼する
【対策①】使用素材は権利がクリアなものを選ぶ
ノベルティ制作において最も重要なのは、使用する素材が「商用利用可能」かどうかを確認することです。
ロゴ、イラスト、フォント、写真、キャラクター、キャッチコピーなど、すべてに著作権や商標権が関わってくる可能性があります。
安易にインターネットから画像やロゴを拾って使用するのはNGです。
信頼できるフリー素材サイトや、商用利用が明記されている有料素材を使うのが原則となります。
また、社内で作成した素材でも、外部から持ち込まれたものには注意が必要でしょう。
「どこから来た素材なのか」「使用許諾は明示されているか」を確認し、“グレーゾーンの素材は使わない”という判断基準を社内で徹底することがトラブル防止に直結します。
【対策②】制作時にチェックリストを活用する
商標トラブルを未然に防ぐには、制作の段階で法的リスクを見落とさない仕組み作りが欠かせません。
その一つとして「チェックリスト」の活用をおすすめします。
たとえば以下のような項目を盛り込んでおくと、確認漏れを防げます。
① 使用しているロゴや名称の出所は明確か?
② 登録商標でないかを調べたか?
③ 使用許可があるか?
④ 類似表現になっていないか?
⑤ デザイン素材の商用利用条件を確認したか?
チェックリストは紙でもデジタルでも構いませんが、関係者が見られるように共有しておきましょう。
また、制作物が複数ある場合は一つ一つに個別で記録を残しておくことが大切です。
仮にトラブルになったとしても、「事前に確認していた」という記録があることで、対応がスムーズになります。
【対策③】信頼できる制作会社に依頼する
ノベルティ制作を外注する場合は、法律リスクに配慮できる制作会社をパートナーに選ぶことが重要です。
経験豊富な会社であれば、商標や著作権に関する相談にも対応してくれるほか、素材の使用範囲について詳しく説明してくれるでしょう。
また、発注時には「誰がどこまで責任を持つのか」を明確にさせることも忘れてはいけません。
たとえば、商標のチェックは発注側が行うのか、制作会社が行うのか、万一トラブルが発生した際の責任分担はどうなるのかなど、契約書や発注書などに明記しておくことが安全な取引の鍵になります。
「とりあえず任せる」ではなく、リスク共有の姿勢で協力できる制作パートナーを選ぶことが、長期的なトラブル回避につながります。
商標を正しく理解して信頼されるノベルティ制作をしよう
この記事では、ノベルティ制作に関わる商標の基本知識や注よくあるNG例、トラブルを防ぐための対策について解説しました。
商標の登録や使用に関しては、一定のルールがありますが、状況によって対応が異なるケースも多くあります。
詳細については、弁理士や専門の法律家にご相談いただくことをおすすめします。
商標リスクをきちんと把握し、ノベルティを安全かつ効果的に活用して、企業の信頼と価値を高めましょう。
ノベルティ制作をするならコシオカ産業
弊社・コシオカ産業はさまざまなノベルティを手掛けております。
弊社は、選りすぐりのデザイン事務所やプロモーション会社、ブランディング会社と提携し、お客様のニーズ・想いに合わせて最適な企画・デザインを提供しております。
また、商品企画からデザイン、設計、生産までを一貫して行っているのも弊社の強みの一つです。
お客様の気持ちに寄り添った提案を心がけておりますので、初めて制作する方でも大丈夫です。
ノベルティ制作を考えている方は、ぜひ一度ホームページからお問い合わせください。
\ノベルティ制作の実績多数!/





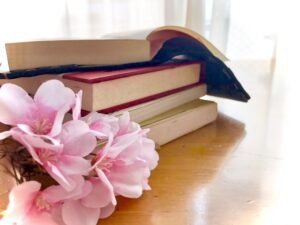




 0120-577-665
0120-577-665